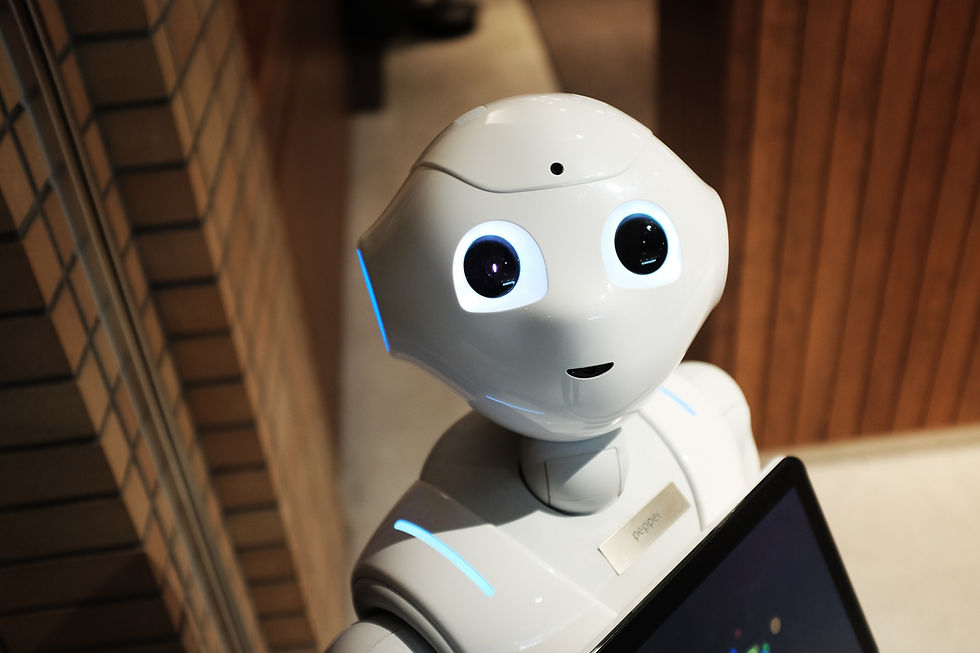井上恵次という師
- Yoshiharu Azuma

- 2023年5月1日
- 読了時間: 2分
更新日:2023年5月8日
既に1カ月以上も前になるが、私は本当に嬉しかった。日本経済新聞の「私の履歴書」に井上恵次(故人)の名を見たからである。JR九州相談役 唐池恒二氏のJR九州外食事業部立て直しの際に、徹底的に読み込み参考にしたのが故人の著書「食堂業 店長の仕事」(柴田書店 93年)だったという。
我々外食コンサルティング業は、当然ながら、表には出ないものであるから、その名を見た時は純粋に嬉しかった。
飲食店の「店舗や企業の組織運営の考え方と技術論」を体系化したのが、 井上恵次である。そのベースとなっているのは、ペガサスクラブを設立し大手スーパーや専門店チェーンを導いた渥美俊一氏のチェーン理論である。学生の頃から渥美氏と親交のあった井上は、柴田書店に入社し『月刊食堂』の創刊に立ち会う。その後、『月刊食堂』は萌芽期のチェーン化を目指す飲食店の羅針盤として、その地位を確立していくことになる。
38歳の時、ロイヤル(現ロイヤルホールディングス)の創業者江頭匡一にスカウトされ、ロイヤルホストの全国展開を担うことになった井上にとって、それは「外食をチェーン化する実践の場」だった。
重要なのは、政策論に留まりがちだった渥美氏の教えを、店舗運営の具体的方法論(ストアマネジメント技術論)に昇華させることだったと、彼は語ったことがある。店舗の運営技術と政策が繋がらない限り、企業の目指す方向には進めないのである。多店化を目指す多くの企業が頓挫するのは、規模の拡大と共にストアマネジメント技術のブラッシュアップが出来ず、1店当たりの売上高が低下していくからである。
「チェーン化の理論を店舗運営に必要な技術論に高めた」ことが、井上恵次の最大の功績だと、私は考えている。井上の著書は全て、「現場の技術論と現場を支える本部の組織運営の在り方」に終始している。
それは、井上の薫陶を直接受けた我々にしか伝え続けていくことができないことなのだと、改めて思う。
ちなみに、唐池氏の片腕として力を発揮したのは、若くしてロイヤルの総料理長を務め、後に井上と共にコンサルタントとして活躍した中園正剛氏(故人)だった。

当社にて販売している書籍
・店長の仕事 井上恵次(著) 《柴田書店 刊》
・食堂業の店長塾 井上恵次(著) 《柴田書店 刊》
・フードサービス用語辞典 井上恵次(著) 《柴田書店 刊》
・店長を育てるエリアマネジャーの仕事 井上恵次(著) 《柴田書店 刊》
・フードサービスのマネジメントがわかる本 東 義晴(著) 《柴田書店 刊》
・新装版 「こつの科学」 杉田浩一(著) 《柴田書店 刊》